~ 障害観 ~
期末テスト、ご苦労様でした。
今回のテストはなかなかに厳しい結果でした。もちろん大きく成績を落とした生徒さんはいませんでしたが、大きく成績を伸ばした生徒さんも2,3名のみ… ほとんどの生徒さんは現状維持でした。平均点、とくに英語の平均点がどの学校も低い傾向にあることなどを考えれば、多少順位は上がるでしょうが、それでも多少かと思います…
中学生のおよそ4割程度は400点を超えておりますが、450点を超えてくる生徒さんはまだ少数… また300点台で足踏みしている生徒さんも多くいます。なんとか7割の生徒さんを400点以上に、各学年3名ほどは450点を取ってもらえるように、今一度学習内容、授業の進め方などを講師陣と相談し、改善していきたいと思います。
その一環として、先ずはこの7月を「英語長文強化月間!」とします。
初見の英語長文が読めない原因の第一は、英単語・熟語の不足でしょう。英単語・熟語の練習に関して、普段は各学校の教科書に沿って暗記、テストを行っていますが、いまいち体系的になっていませんし、最近の教科書に出てくる単語が高度になりすぎて、どれが基本単語なのかもわかりずらくなっています。ですから、7月はごく一般的な基本単語・熟語を中心にしっかりと覚えて頂こうと思います。その上で、英文法です。しかし、英文法は普段から塾でもしっかりと取り組めていますし、弊塾の皆さんは結構できていると思います。ですから、ここはとりあえず7月中は省略。英文中に出てきた文法を都度確認するにとどめたいと思います。最後は一般常識の不足です。大人になるになると、ニュース等でなんとなく世間一般によく出てくる話題、その問題点、大まかな解決法などを覚えていきます。学校や受験で出てくる文章はごくごく常識的なものばかりですので、この一般常識があれば、英単語、英文法がいまいちでも、ある程度読めてしまうのです。
これらを体に例えてみますと、英文法は骨格、英単語は筋肉、そして一般常識は頭脳なのだと思っています。先ずはしっかりとした英文法(骨格)が必要です。そして、これはある程度しっかりと学んだら、それ以上はなく、固定されます。そこに英単語・熟語(筋肉)を付け、鍛えていきます。もちろん限界はありますが、ここは鍛えれば鍛えるほど強くなりますし、より早く、より深く文章を読み込むのにどうしても必要です。そして、一般常識(頭脳)、これは普段からニュースを聞いたり、家族で話し合ったりする。もしくは、より多くの英文、国語の問題文を読むことによって増えていきます。いわゆる「多読」です。
ここが弊塾で、普段なかなかできていないところかと思いますので、7月中は、「多読」と英単語・熟語の強化月間にしていき、8月31日(日)に予定しています、模擬テストでは、一歩上のレベルに達してもらえたらと期待しております。
今月も『怠けてなんかない! ゼロシーズン(2011年 岩崎書店)からディスクレシアについて学んでいきたいと思います。今月も、筆者のコラム( p40)からです。
まず、俳優のトム・クルーズやウービー・ゴールドバーグ、政治家のチャーチル、作家のアンデルセン、オリンピック水泳金メダリストのマイケル・フェルプスなどは、いずれもディスクレシアやADHDなのです、彼、彼女たちのことを「障がい者」だと思いますか?
ほとんどの方は障がい者だとは思わないと答えるかと思います。実際、この本の筆者がおよそ5万人の方に同じ質問をしても、ほぼ全ての人が障がい者だと思わないと答えたそうです。
では、「なぜ障がい者だと思わないのか?」との質問に、「社会的に成功しているから」「社会に参加しているから」「社会に貢献しているから」「好きなことをやっているから」「自己実現しているから」などの答えが返ってくるそうです。
ここから逆に、日本人が持っている「障害観」、つまり「障害」と聞いたときに無意識に思い浮かぶ言葉、感情は、「成功できない」「社会参加できない」「社会に貢献できない」「自己実現できない」というものになるかと思います。
実際、友人の聾唖者に聞いた話では30年ほど前の日本の聾学校では、2学年ほど遅れた教科書を渡されていたそうです。(全ての聾学校ではありませんが)つまり、耳が聞こえづらいと言うだけで、そのまま知能も遅れているはずと捉えられ、実年齢よりも下の学習を強いられていたのです。これもその根底には、日本人の「障害観」があったのだと思います。(ちなみにその方は現在公立学校の先生として勤めています。)
たしかに成功するかどうか、自己実現できるかどうかは、障害の有無にかかわらず難しいものです。しかし、社会に参加できるかどうかは、その社会を構成している人たちのちょっとした気遣い、思いやり、社会制度を整備すればほぼ実現できることでしょう。そして、子どものうちならば、その苦手を発見し、その苦手・特性をとらえた適正指導をしていくことで、より自立した一人の大人になってもらえるはずです。
しかし、いまだに日本では、各人の個性、特性に合わせた教育、またインクルーシブ教育の実現、そして障害の有無にかかわらず、同じ地域で共に暮らせる社会や企業が実現できるいるとは言いがたいかな?と感じております。多くの人たちが
共に暮らせる社会や教育を目指して今月も頑張っていきます。
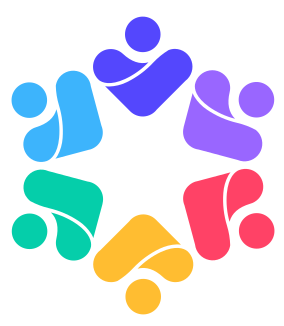 やまと学院.
やまと学院. 

